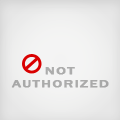TechCrunch Japanese アーカイブ アマゾンKindle延べ販売台数は「24万台」だった
アマゾンに近い筋から得た情報によると、昨年11月からのKindle出荷数は延べ24万台だそうだ。(中略)ザックリ計算してみると、この端末の総売上高は通算$86M(8600万ドル)から$96M(9600万ドル)の間となる(端末価格はこの5月に$400から$360に切り下げとなった)。 これに利用者が端末上で読むデジタル書籍、新聞、ブログの購入に支払った額を加算すると、これまでだけでも$100M(1億ドル)を楽勝で超えるビジネスということになる
AmazonがKindle(キンドル、と呼びます)を発表したときは、冷ややかな見方が広がっていたように思いますが、半年強で24万台も売れているらしいです。これを金額に直すと、100億円近くにもなります。さらに有償販売の合計額も同程度あり、Amazonは、ゼロから半年強で200億円のマーケットを生み出したことになります。
電子書籍端末売れず──ソニーと松下が事実上撤退 - ITmedia News
松下電器産業とソニーがそれぞれ、専用端末を使った電子書籍から事実上撤退することが分かった。ソニーは昨年、松下は今年3月までに端末生産を打ち切り、書籍ダウンロードサイトは今年度中に閉鎖する。
(7月初めのニュースですが)一方で、日本勢は松下もソニーも撤退します。Kindleが、日本メーカーと違った点は、まず開始時にベストセラーを含む9万冊という大量の書籍を準備したことと、ネットワーク機能が搭載されておりダウンロード購入も24時間いつでもどこでも手軽にできるという点です。
これを補足すると、KindleにはノートPC用のデータ通信カードのようなものが内蔵されており、月額無料で提供されているということです。なぜこういうことができるかというと、Kidle自体はコンテンツを有料販売するので、通信費をコンテンツ費に上乗せできるし、ノートPCのように膨大にデータ通信をしないためにキャリア(ドコモとかKDDIとかの通信事業社)もネットワークに負荷をかけないために1台辺り相当安く提供できるからです。
ユーザー視点でみると、端末がカラーだろうが小さかろうが(とりあえずは)関係なく、どれだけの読みたい書籍がどれだけ「簡単に」買えるかが重要なのであり、Kindleはこの二つを見事にクリアしています。
その点、上記のITmediaの記事ですらメーカー広報が「専用端末の大きさや重さがユーザーに受け入れていただけなかったのだろう」と言ってしまうのだから、その差はどこまで広がっているのかと。。
どうやら、日本メーカーは、iPodに続いて、電子書籍というマーケットのおいしい部分も失ったようです。もうそろそろルールを変更するような「ものづくり」をしていって欲しいなと思います。
追記:3月にApple増井さんに触らせてもらったKindleの写真。アシンメトリーな形をしているのが印象的でした。反応はきびきびしててよかったです。

Kindle posted by (C)Shintaro